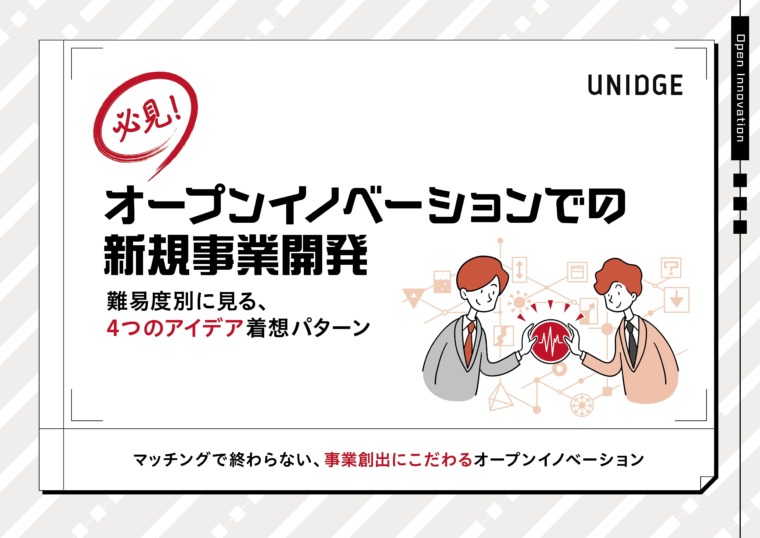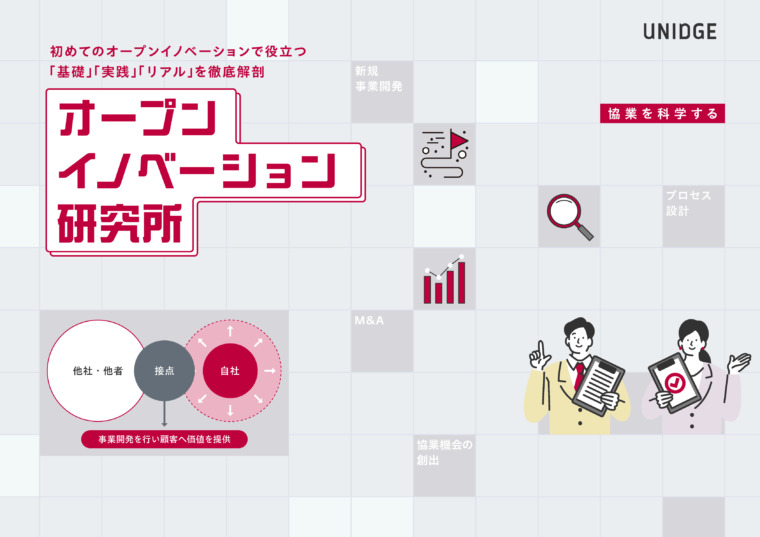導入
起案者、そして事務局やメンターが新規事業の創出に挑む中で、多くの人が抱える悩みや課題がある。その解決のヒントを提供しているのが、新規事業開発支援を行うAlphaDriveの「新規事業よろず相談室」だ。第12回目となる今回のテーマは「DX×新規事業開発」。DXの文脈をまとって始動することも多い新規事業創出だが、活用したいアセットが自社になかったり、社外向けの開発実績がなかったりと、悩み、行き詰まりがちだ。相談室に寄せられたお悩みに答えていく。
最大のアセットは「顧客」。それでも変わらない場合の最終手段は「社内政治」
お悩み1:新規事業に活用したいアセットが自社にない
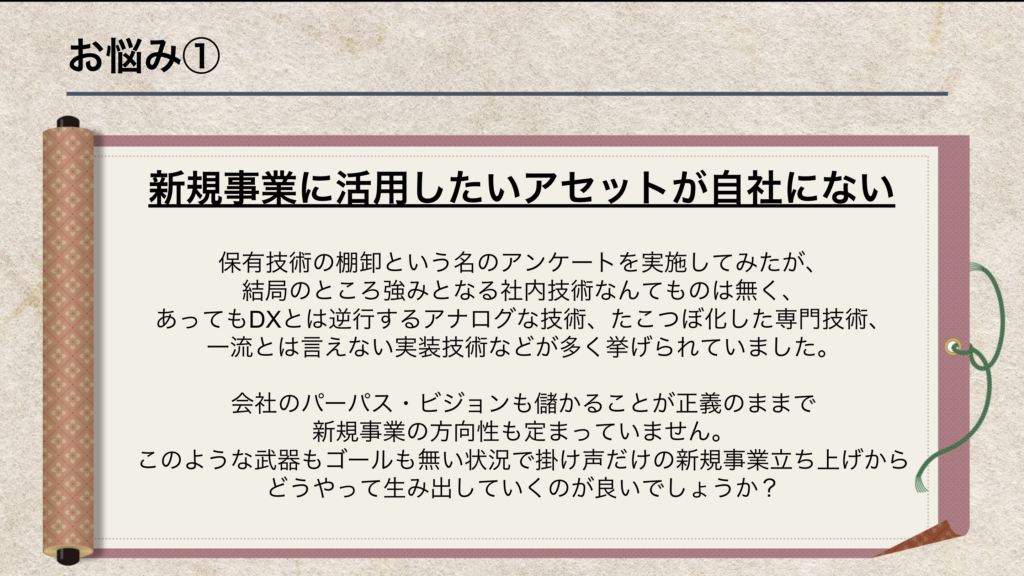
古川:新規事業開発を進めるに当たり社内の保有技術の棚卸しをしたが、活用したくなるアセットがなかった、というお悩みです。
麻生:大前提として新規事業開発における最大のアセットは、「技術」ではなく「顧客」であるということです。既存事業ですでに課題を解決し、喜んでくれている顧客がいる。その状態こそが、最大のアセットなのです。このことを踏まえると、つながっている顧客に対して「より新しい課題解決となるような商材を仕入れてきて提供する」「協業でPoC(Proof of Concept、概念実証)してみる」など、新規事業開発の方法はいくらでもあるのではないでしょうか。
古川:その通りだと思います。しかし、さまざまな事情から既存顧客をアセットとして活用できないケースも中にはあります。例えば、新規事業開発のための顧客ヒアリングをしようとしたら「大事な取引先にそんなことするな!」と反対意見があったり、自社の営業網・販売網をアセットとして起案したけれど「新規事業のためには動かせない」と断られてしまったり。そもそもアセットを新規事業に活用すること自体を言い出しづらい空気さえ、会社の中に充満していることもあると思います。
麻生:この相談者は、どのような状況なのでしょう?
古川:新規事業よろず相談室では、投稿アプリを使い視聴者とのインタラクティブなコミュニケーションをとっているのですが、相談者本人から補足が入りました。「アセットを活用する前提で動いており、自社の顧客は『中間の販売会社』なので、エンドユーザーに直接アクセスできない」という状況のようです。
麻生:なるほど。製販分離のメーカーに勤務しているケースですね。その場合はたしかに難易度が高いかもしれません。カスタマーと直接の接点が持てないし、アセット活用前提で新規顧客にもアプローチしにくい面もあります。
古川:最終顧客にアプローチできないとなれば課題発掘が難しいですが、おそらく相談者の会社周辺にも取引先となる販売会社、生産パートナーがいると思います。その方面で検討するのはいかがでしょうか。
麻生:おそらくこの相談者のケースがそうですが、新規事業開発プログラムの前提や立てつけが間違っている可能性もあります。相談者は限られた条件の中で「なんとかしよう」と奮闘していることが想像できますが、何をするにしても行動が封じられている状況であれば、攻略すべきは「社内」です。プログラムをつくる上の役職に近づき「ひたすら飲む」、そして仕組みを変えてもらえるよう「ひたすら説得する」。そのような社内政治が功を奏する場合もあります。
社内向け技術の「そのまま外販」はNG
お悩み2:社内向けの技術を事業化するには?
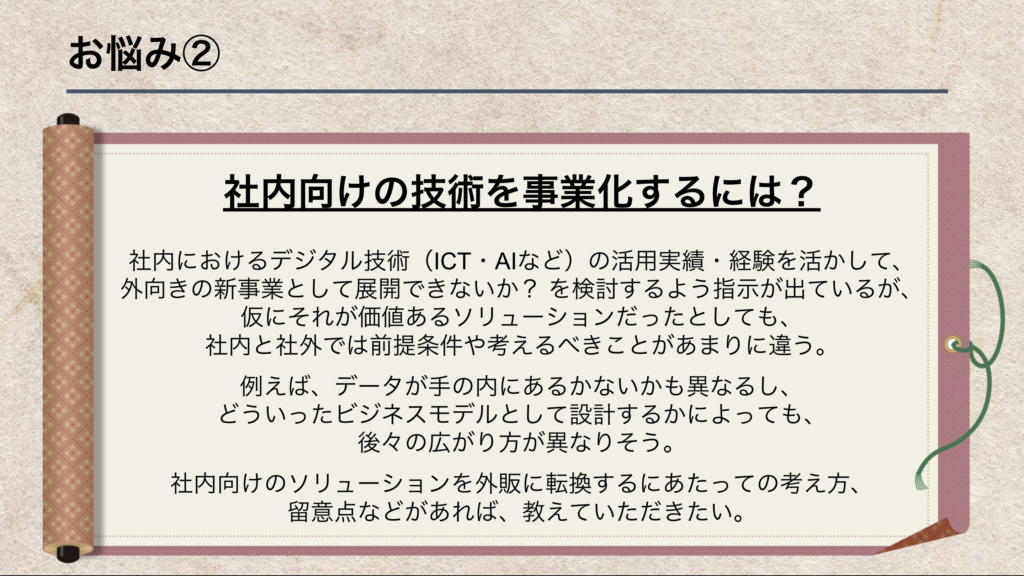
古川:既存の社内向けソリューションを新規事業で外販展開する場合は、どのような点に留意すべきでしょうか。
麻生:相談内容を見ると、「社内・社外では前提条件が異なる」「データの在りかやビジネスモデルが違う場合もある」という点を気にしているようですが、まずは自社と同じような課題を抱えていそうな会社にそのソリューションを持っていき、「いくらで買ってくれますか?」と聞いてみてはどうでしょう。それをきっかけにすれば、そのソリューションに対する理想と現実のギャップが見え、仮説と顧客検証を回すことができるようになります。
古川:ただし、「社内向け」の前提条件でソリューションを組み立てているため、言うほど簡単にはいかないかもしれません。
麻生:たしかに社内システムは、その会社の業務フローを前提としており、「スパゲティ化(処理の流れや構造が絡まっていて把握しにくい状態になっていること)」しているケースもあります。すでにつくられたデータベースやシステムセットをそのまま外販するのは難しいです。社内におけるデジタル技術の活用実績・経験は存分に生かすべきですが、社外向けに販売するときはその技術をそのまま活用するのではなく、「同じものをゼロから組み立てる」が基本姿勢になります。例えば、株式会社リクルートと株式会社サイバーエージェントの合弁会社である株式会社ヒューマンキャピタルテクノロジーは、「Geppo(ゲッポウ)」という個人や組織の課題を見える化するサービスを展開しています。これはもともとサイバーエージェントが社内向けに開発したソリューションで、同社内で使われていた名称がそのままサービス名になっています。名称は同じですが、サービス展開しているGeppoは、社内向けのものとは別に開発されています。
古川:社内向けソリューション・技術の事業化に関しては、そのソリューションや技術によって「社内の何を解決できたのか」が重要なのだと思います。同じ悩みを持っていれば、そこに外販できるだけの可能性があるはずです。しかし、麻生さんが答えたように、そのままのかたちで販売するのは難しいのが現実です。社内向け開発で得た実績・経験、さらには考え方、ノウハウなどを生かしながら、新たに事業開発するのがベターなのではないでしょうか。
DXをまとった新規事業開発は「負の側面だけではない」
お悩み3:顧客課題起点ではなくツール起点で事業開発を進めてしまう
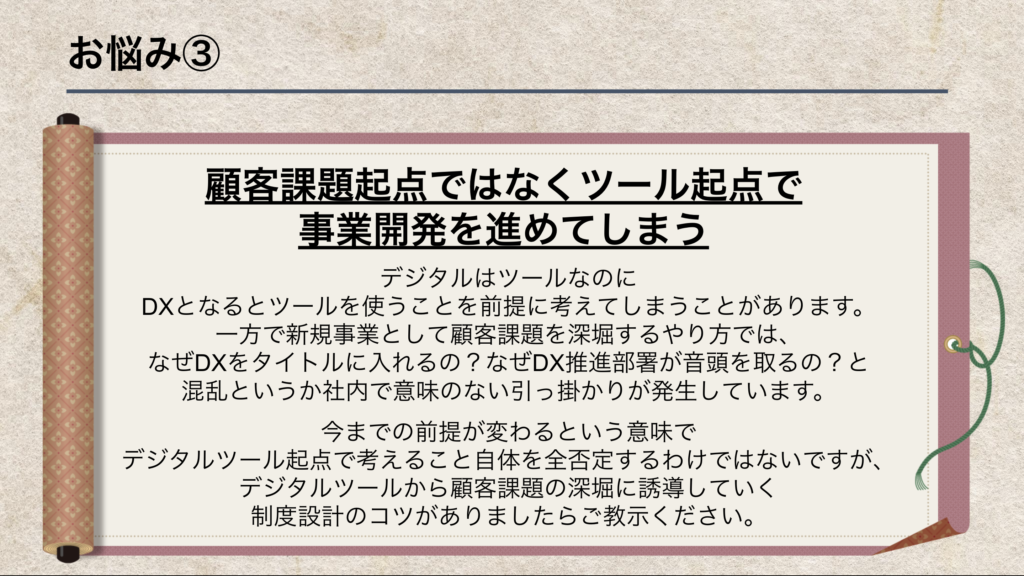
古川:前提として、新規事業開発は顧客課題起点であるべきです。しかし、DXを絡めた新規事業開発では、「デジタルツールありき」で事業開発が進められがちです。今回のテーマ「DX×新規事業開発」として、かなり普遍的なお悩みといえるかもしれません。
麻生:これに関しては、事務局のお悩みか、当事者のお悩みかで回答が異なります。まず当事者向けに答えるならば、「顧客課題起点でないと新規事業開発はできない」ということです。顧客課題起点は新規事業開発における「絶対条件」なのです。しかし会社からDXを求められるなら、報告資料やプレゼン資料1枚目のタイトルに「AIを活用した〜」や「サブスクリプションビジネスの〜」など、DXに関係ありそうなワードを後づけでよいので入れておくのも一手です。DXに取り組んでいるふりをしながら、顧客の課題解決に取り組みましょう。次に事務局向けです。「デジタル起点で考えたプログラムにしろ」と上から言われているケースです。この場合は、最初に実施する起案者向け説明会などの冒頭でDXの話をしましょう。解決策の本質は、当事者の場合と同じです。
古川:つまり、いずれにせよDXを「まとう」ことが重要ということですね。あくまでポーズ(外面)として、会社や上司の意向に沿うことも必要である、と。
麻生:はい。もう1つ小手先の技を伝授します。まずトータルで1時間の説明時間があるとしたら冒頭5分間にAIの話をしましょう。例えば「AIはデータが集まらなければ始まらない」「正解・不正解を導くためにはデータが必要」「そのためには顧客課題にフォーカスすることが重要」という筋書きです。そして最後にもう一度AIソリューションの事例の話を入れてもよいでしょう。そうすることで、その新規事業開発プログラムは「DXに関係している」ことになります。今の時代、顧客課題起点でソリューションをつくっていけば、大多数のケースで「デジタルを活用する」ということに着地します。文脈として、利用できるのではないでしょうか。ともあれ、新規事業開発の前半戦は「アナログかつ手づくりで顧客課題を解決し、その顧客に喜んでもらえるところに商機がある」というアプローチでないと、本質に目が向かいにくいです。そのときDXと銘打つこと(まとうこと)で、事業の拡張性や競争優位性などが織り込まれながら設計されます。この点から、「DXをまとった新規事業開発」はポジティブな側面もあります。堂々とまとってください。
「自社アセットと無関係だからNG」の本質は戦略合理性と競争優位性
お悩み4:ソリューションとしてテックが必要ない顧客課題だった場合
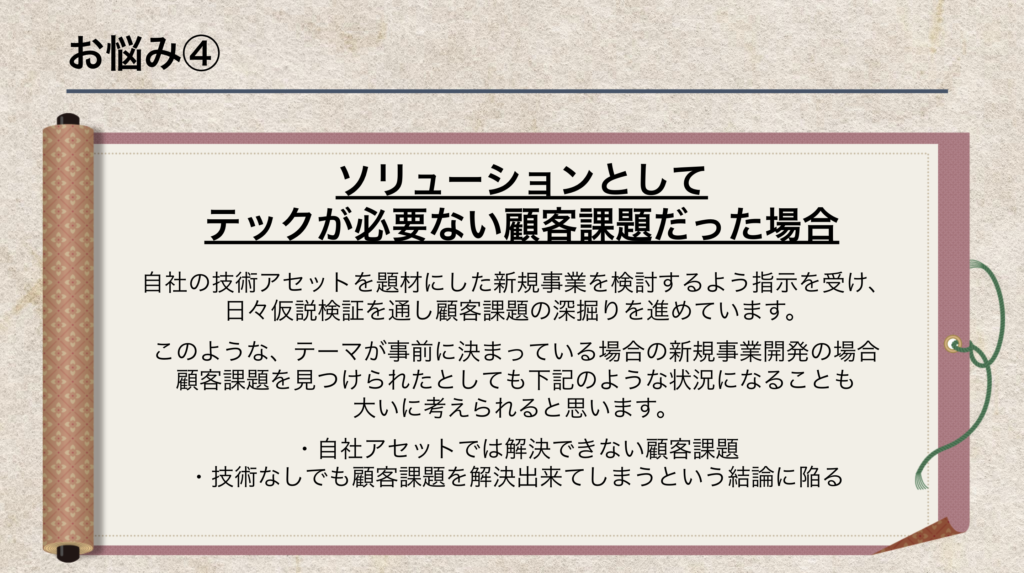
古川:次の課題は、テックを必要としない顧客課題についてです。
麻生:「技術なしでも顧客課題を解決できてしまう」とは、どういう場合でしょう。すぐには思いつきません。
古川:「自社の技術アセットを題材とした新規事業を検討」との前提があるようなので、単にサイトをつくればよいという話ではないと推測できます。もっと専門的・科学的な技術アセットが題材になった新規事業開発で、「顧客課題を見つけられたとしてもそれを自社アセットでは解決できない」という内容の悩みなのかもしれません。
麻生:(前編の)お悩み1にも関連するかもしれませんが、何がなんでも「自社のアセット起点」で進める事業開発は、難しいです。なぜなら課題やソリューションがピポットするたび、必要とするアセットが変わるかもしれないからです。自社アセットしか使えないのだとしたら、行き詰まるたびに課題の発掘に立ち戻らなければいけなくなり、時間も費用も労力もかかります。これが単に「解決したい課題はあるけれど、自社アセットでは解決できない」というだけならば、他社アセットを活用した協業やオープンイノベーションの道があるのですが。
古川:中には「オープンイノベーションでは主導権が握れないから避けたい」という企業もあるかもしれません。
麻生:その場合は、オープンイノベーション先をM&Aなどで取り込んでしまうという方法がありますが、それも難しいのであれば、先ほどお伝えした通り、自社アセットが適さないと分かるたびにスタート地点に戻る道しかないと思います。
古川:今回、アセットの話が何度も出ていますが、私の印象では「自社アセットを活用した新規事業を会社がかたくなに求めているか」といえば、実はそうでもありません。自社アセットを活用してほしいと言われる背景は、ステークホルダーに向けた「戦略合理性」として自社でやることの動機付けにしたいという思惑や、「競争優位性」として自社の強みで勝負したいという思いがあるからです。この思惑や思いさえクリアできれば、必ずしも自社アセットにこだわる必要はないという場合も多いのではないでしょうか。もう一段階上の本質から、見直してみてもよいのかもしれません。
麻生:その通りです。例えば、最終審査会などで「当社で取り組むことではない」との判断が下ったとしても「かなり感動する、儲かる仕組みもある」という事業アイデアだった場合、その判断が覆ることは、結構あります。中には、「最近買収した企業のアセットが使えるかもしれない」というように、トップマネジメントからアセット活用の提案があることもあります。特に「感動する」事業アイデアでは、そういうことが起こり得ます。
デジタルリテラシーが低い会社のチームづくり作法
お悩み5:推進者の人材要件・DXリテラシーのポイント
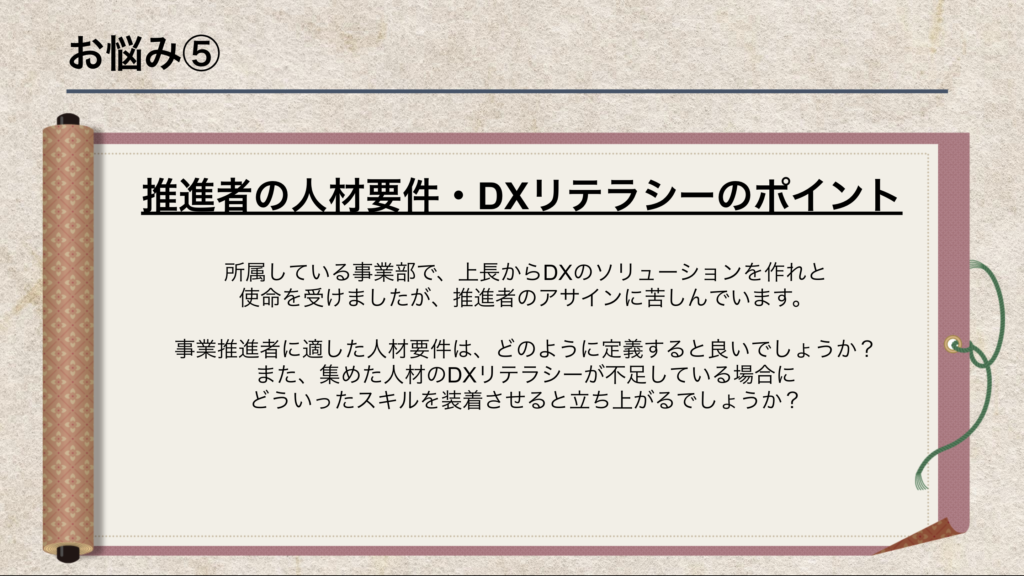
古川:最後は、DX推進者のアサインに苦しんでいるというお悩みです。
麻生:人材要件については、プログラミングができることに越したことはありませんが、自分でコードが書けたり、自分で技術を操れたりする必要はありません。必要なのは、主たる技術要素がどのようなコンセプトでつくられ、どのような課題を解決し得るのか(どう使えるのか)を、ビジネスパーソンとして理解した上で、組み合わせてプロデュース・企画できる素養です。AIとは何か、ブロックチェーンとは何か、はたまたWeb2.0とWeb3.0は何が違うのかということを説明できる程度のリテラシーがあれば、誰でもいいと思います。さらに、このお悩みを深掘りした仮定の話をしてみましょう。相談者の投稿文からは詳しい事情が分かりませんが、仮にこの相談者の会社が「全てを紙で管理している」くらい、デジタルリテラシーのない会社だったとします。そのような会社で「DXソリューションをつくれ」とのお達しが下りました。どうすればよいでしょうか。繰り返しになりますが、DXに着眼した新規事業開発でも課題は必ず現場にあります。しかしこの会社の場合、現場の末端まで「デジタルリテラシーが低い」という状態です。その場合は、まずはDX推進者を1人選任し、現場の側にもDXの窓口チームを置きます。デジタルに関してある程度の知識を持つDX推進者の役割は、現場に対して質問し「このような技術を導入すると、このようなことが可能になる」と唆すこと。現場側にその窓口があれば、DX推進者と現場の間でのハレーションも起こりにくいはずです。
古川:なるほど。その考え方には共感します。その上で、あえて新規事業開発プロセスの一般論として追加すると、専門的なデジタル技術やDX知識を必要とするのは、事業推進していく中のごく限られた範囲です。役割が細分化されたフェーズで考えるべきことでしょう。よって、デジタル技術やDXの素養のある人間をアサインした先に、DXを活用した事業が生まれるのかといえば、必ずしもそうではありません。それよりも、事業開発スキルを持っている人たちを中心に据えることが先決です。
Q&Aセッション
以下、その他に寄せられた質問に短くお答えします。
——新規事業開発に当たり顧客起点のアプローチを提案しています。しかし会社から「戦略を練るのが先」と言われ、なかなか前に進みません。どうすればよいのでしょうか。
麻生:わざわざ社内承認なんかとらず、まずは会社に黙って顧客のもとへ行ってしまいましょう。それすらも許されず、先に活動方針などを提出する必要がある状況ならば、言われた通りにつくればいいだけのことです。この場合は「当社AI技術を活用する場合、その1、介護マーケットのデータを活用したらこうではないか。その2、工場の生産現場にこういうデータがありそうだからこうではないか。その3、学校の教育現場の動向はこうではないか」といった具合に、20通りくらいにセグメント化した仮説を「それっぽく」作成するとよいでしょう。
古川:私の本音も「資料なんてつくらず顧客のところへ行け」です。現実的に皆さんは会社員であり、資料をつくり、上司の承認を得なければ動けないという現実があることも理解できます。しかし、新規事業開発のプロセスではそうしたシーンがついて回ります。だからこそ私が強調したいのは、「資料作成があるから顧客のところへ行けない。前に進めない」と嘆くのではなく、「つじつま合わせに時間を使うべきではない。資料は適当につくり、早く顧客のところへ行く」です。
——事業開発スキルとは、具体的にどのようなスキルでしょうか。
麻生:シンプルにいえば、新規事業にはステージがあり「WILL期(アイデア創出)→MVP期(顧客課題実証・ソリューション実証)→SEED期(事業性実証)→ALPHA期(事業拡大)」と続いていきます。AlphaDriveでは各ステージで求められるスキルを定義し、「事業開発スキル」としてまとめています。例えば、前半戦では新規事業と原体験をひも付けるスキルや顧客のもとに何度も通い仮説検証を繰り返すスキルが必要です。また、後半戦ではそれらスキルは必要なく、また別のスキルが求められていきます。ステージごとに求められるスキルが変化していくのが、ポイントです。
——製販分離のケースにおける、顧客差セットの利用についてもう少し教えてください。
古川:たとえ製販分離のメーカーでも、エンドユーザーに会うことは可能だと思います。ただ製販の「販」との関係性を考慮し、「会いに行きづらい」という事情があるのでしょう。
麻生:打開策があるとすれば、「外部パートナーを使う」です。製販の「製」のメンバーのみでエンドユーザーに会いにいくことに当たり障りがあるのであれば、外部のコンサルティング会社などを使い、その人たちにヒアリングしてもらうのはどうでしょう。いつもの名刺ではなく、コンサル用の名刺を用意して会いに行くのも手です。
古川:ヒアリングは新規事業開発を行う会社のチームが実施するのが、ベターです。麻生さんの言う通り、「別の顔」を持つのが1つの正解かもしれません。別の方法としては、「販」を巻き込むこと。具体的には社外メンバーとして加わってもらいましょう。この方法が正攻法かもしれません。
筆者について

麻生 要一
株式会社アルファドライブ 代表取締役社長 兼 CEO
東京大学経済学部卒業後、株式会社リクルートへ入社。社内起業家として株式会社ニジボックスを立ち上げ、創業社長として150人規模まで企業規模を拡大。 リクルートホールディングスの新規事業開発室長として1500の社内起業家チームの創業と、起業家支援オフィスTECH LAB PAAKの所長として300社のスタートアップ企業の創業期を支援。2018年に起業家に転身し、複数の企業を同時に創業。新規事業支援会社であるアルファドライブは、2019年にユーザベースへ全株式を売却後、2023年にユーザベース自身がファンド傘下へのTOB・非公開化した流れを受け、2024年に全株式を買い戻し再度カーブアウト。 アミューズ社外取締役、アシロ社外取締役などプロ経営者として複数の上場企業の役員も務める。

古川 央士
株式会社アルファドライブ 取締役 兼 グループ執行役員 COO
青山学院大学卒。学生時代にベンチャーを創業経営。その後、株式会社リクルートに新卒入社。SUUMOでUI/UX組織の立ち上げや、開発プロジェクトを指揮。その後ヘッドクオーターで新規事業開発室のGMとして、複数の新規事業プロジェクトを統括。パラレルキャリアとして、2013年に株式会社ノックダイスを創業。飲食店やコミュニティースペースを複数店舗運営。一般社団法人の理事などを兼任。社内新規事業や社外での起業・経営経験を元に、2018年11月、株式会社アルファドライブ執行役員に就任。リクルート時代に1000件以上の新規事業プランに関わり、10件以上の新規事業プロジェクトの統括・育成を実施。株式会社アルファドライブ入社後も数十社の大企業の新規事業創出シーン、数千件の新規事業プランに関わる。2023年より株式会社アルファドライブ取締役兼COO。